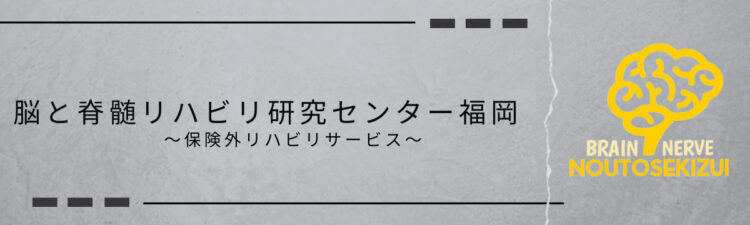この投稿は、『脳卒中・脊髄損傷特化型自費リハビリ施設〜脳と脊髄リハビリ研究センター福岡』が日々脳卒中(脳梗塞・脳出血)や脊髄損傷、脳性麻痺といった神経疾患後遺症のリハビリテーションに従事する医療従事者の方や、当事者の皆様に向けて発信するエビデンス情報です。
私たちは日常生活の中で、「歩く」「立ち止まる」「振り返る」「曲がる」といった動作を自然に行っています。
特に、“方向転換“は、狭い場所での移動や歩行中の軌道修正、ドアの開閉時などに不可欠です。
しかしながら、脳卒中を経験された方の多くが「歩く時に真っすぐは歩けるけど、方向を変えるのが苦手」という悩みを抱えています。
例えば…


実は、転倒事故の多くは“方向を変える時“に起きていることが分かっています。
方向転換が上手くいかないと、転倒リスクが高まるだけでなく、日常生活の自立や外出機会の減少にも繋がってしまいます。
今回紹介する論文は、こうした課題に対して方向転換に特化したトレッドミルトレーニングが歩行の質を大きく改善する可能性を示した、非常に興味深いものです。
【脳卒中リハビリ】真っすぐ歩くだけじゃ足りない!“方向転換トレーニング“の力
参考文献
今回の論文は2013年7月に発表された論文です。
Turning-Based Treadmill Training Improves Turning Performance and Gait Symmetry After Stroke
研究の概要
対象者
- 慢性期(発症6ヶ月以上経過)脳卒中患者30名(平均年齢:62歳)
以下の条件の方を対象
(a)初発脳卒中後6ヵ月後で片側の運動障害があること
(b)歩行補助具の使用有無にかかわらず、少なくとも6mの自立歩行が可能であること
(c)患部下肢のBrunstrom stageが3以上であること
(d)言語による指示に従うことができること
割付方法(無作為に以下の2群に振り分け)
- TBT群(ターン特化型トレッドミル訓練)
- CT群(通常の直線歩行トレッドミル訓練)
介入内容
- CT群(通常歩行群)
• 一般的な直線型トレッドミルでの歩行訓練
• 歩行速度・時間はTBT群と同等に設定
- TBT群(ターン訓練群)
• 特殊な円弧型トレッドミル上を歩行(麻痺側内回り・麻痺側外回り)
• 回転速度は個々に応じて調整
⇒各人が平地で快適に回転できる速度から開始し、耐えられる範囲で 5 分毎に 0.05 m/s ずつ増加させた。
トレッドミルの速度:0.15〜2.80 m / sの範囲
介入頻度:各々30分間(トレッドミル訓練)を受けた後、10分間の一般的な運動プログラムを4週間にわたって12回受けた。
参加者は両方向にトレーニングし、患部の脚を内側の脚として 15 分間、次に外側の脚として 15 分間、その間に 5 分間の休憩を挟む。
患肢を内側または外側の脚として歩く順序は、連続するセッション毎に交互に行われた。
評価項目
介入前後で以下の評価を実施。
- 方向転換能力
・180度方向転換に要する時間、ステップ数、歩行の対称性ステップ長の左右差(麻痺側内回り・麻痺側外回り)
- 筋力
股関節屈筋/伸筋/外転筋、膝屈筋/伸筋、及び足首背屈筋/足底屈筋の筋力
⇒ハンドヘルド ダイナモメーター にて測定
メイクテスト方法:被験者が最大限の力を加えている間、検査官がハンドヘルドダイナモメーターを静止させたままにする。
各筋肉について、3 回 5 秒間の収縮のそれぞれで生成される最大力を平均化
研究の結果
- 方向転換能力
•回転速度
どちらのグループも、トレーニング後に患側と非患側の両方への回転速度を改善
TBT群:方向転換速度の改善
麻痺側内回り平均速度が0.45 ± 0.17 m/sから0.81 ± 0.24 m/s
麻痺側外回り平均速度が0.47 ± 0.13 m/sから0.82 ± 0.24 m/s
・歩幅とケイデンス
TBT群:歩幅の延長、ケイデンスの増加(P < .001)
・立脚時間の左右差
TBT群:麻痺側立脚時間の延長、時間的非対称比 の改善(P = .044)
- 筋力
TBT群:筋力の改善
股関節屈筋(P = 0.037)、股関節伸筋(P = 0.027)、股関節外転筋(P = 0.032)、足関節背屈筋(P = 0.007)
更に、同様のトレーニング方法を用いた追加研究で以下の改善効果についても明らかになりました。2019年に発表された論文です。
Novel gait training alters functional brain connectivity during walking in chronic stroke patients: a randomized controlled pilot trial
評価:特殊な円弧型トレッドミル上を歩行。
脳波(EEG)と筋電図(EMG)の関係性を検証。
結果:時間的対称性(左右立脚時間)の改善により前頭部‐中心部‐頭頂部にかけてのEEG‐EEG、EEG‐EMGの結合が明確に強化
⇒立脚時間の対称性が良くなるほど、脳と筋の結合が強くなることを示した
これらの論文が特別な理由
これらの研究が特別なのは、「方向転換(ターン動作)という“複雑で見落とされがちな動作”に着目し、それをリハビリに取り入れたこと」にあります。
歩行に対するリハビリの多くは直線歩行に焦点が当てられがちですが、実生活では曲がる・回る動作が不可欠です。
特に脳卒中後は、麻痺側の使用が減ることで回旋動作が苦手になり、ふらつきや転倒の原因になります。
本研究は、回転を伴うトレッドミル訓練(TBT)を通じて、ターン能力の向上だけでなく、麻痺側下肢の支持性・歩行の対称性の改善、さらには脳と筋の連携強化まで実証しました。
つまり、方向転換の練習は単なる動作改善ではなく「脳の再構築(神経可塑性)」を伴った、根本的な回復が起きていることを神経生理学的な指標を用いて示した点が非常に意義深いのです。
リハビリへの応用
ご自宅で簡単にできる練習を紹介
- サークル歩行を取り入れた歩行練習
・左右の脚を軸として円弧状に歩行する練習
- 方向転換を取り入れた歩行練習
• 直線→90度もしくは180度ターン→直線といった反復課題
• 右回り左回りをバランスよく取り入れる
- 注意を向けながらの「意識的」な動き
• 曲がる瞬間に、どちらの足で回っているかを感じる
• 足裏や重心の動きに集中する
- 麻痺側を内側にする方向転換練習
•麻痺側にしっかり体重をかけることで、非対称な歩行パターンを修正
- ご自宅での安全なターン練習
• 廊下や家具の間でゆっくり大きく回る練習
• 鏡や動画を使って姿勢やふらつきを自己確認
おわりに
「真っ直ぐ歩くだけがゴールじゃない」
歩くことは、単なる前進だけではなく、「曲がる・止まる・向きを変える」といった多様な動きが組み合わさっています。
方向転換は、私たちが家の中を移動するためにも避けて通れない動作です。
今回の研究は方向転換という「地味だけど難しい動作」にこそ、リハビリの鍵があることを教えてくれました。
もしあなたが、
• 歩いていてふらつく
• 方向転換に不安がある
• 麻痺側をあまり使えていない気がする
そんなときは、ぜひ「方向転換」の動きに目を向けてみてください。
このコラムが、リハビリに新たな視点をもたらすきっかけになれば幸いです。
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡によるセミナーのご案内
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡では、施設での対面式とオンラインを併用して定期的にセミナーを開催しております。
主に、臨床思考力に焦点を置いた「クリニカルリーズニング」、痛みのリハビリに特化した「ペインリハビリテーション」、脳卒中リハビリに特化した「脳卒中リハビリ関連戦略」の3本を定期開催しております。
詳しい内容や日時については、こちらのページをご覧ください。
開催テーマ・日程一覧ペインリハビリテーション-基礎メカニズム編-肩の痛みや膝の痛み、腰痛含め全てのリハビリテーションにつながる”痛み”のメカニズム全ての内容が世界中で行われている研究結果に基づいた講義になっており[…]
皆様の明日の臨床を確実に変えられるような、そんなセミナーとなっております。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡の店舗案内
博多店
住所:福岡県福岡市博多区諸岡3丁目10-20
駐車場:2台
アクセス:西鉄井尻駅から徒歩10分/JR笹原駅から徒歩10分- 小郡店
住所:福岡県小郡市小郡2200-1
駐車場:5台
アクセス:鳥栖JCTから車で5分/JR久留米駅から車で24分
備考:久留米市・筑紫野市/佐賀県鳥栖市・基山町から車で約30分圏内