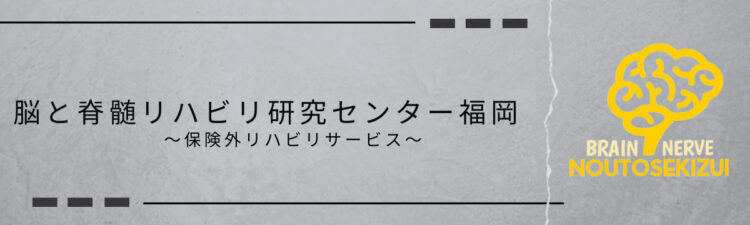この投稿は、『脳卒中・脊髄損傷特化型自費リハビリ施設〜脳と脊髄リハビリ研究センター福岡』が日々脳卒中(脳梗塞・脳出血)や脊髄損傷、脳性麻痺といった神経疾患後遺症のリハビリテーションに従事する医療従事者の方や、当事者の皆様に向けて発信するエビデンス情報です。
【パーキンソン病リハビリ】すくみ足にはタイプがある!?
はじめに
パーキンソン病の方にとって「すくみ足(Freezing of Gait:FOG)」は、転倒リスクや生活の質に直結する大きな課題です。
これまで、すくみ足は一律に語られてきましたが、実はその中に“タイプの違い”があることをご存じでしょうか?
今回ご紹介する研究では、新しい質問票を用いて、すくみ足を「サブタイプ」に分類し、その特徴を明らかにしました。
これは、今後のリハビリや治療をより“オーダーメイド化”する上で大きな一歩となり得ます 。
参考文献
今回の論文は2018年7月に発表された論文です。
vidence for subtypes of freezing of gait in Parkinson’s disease
研究の概要
対象者
すくみ足を有するパーキンソン病患者 41名
方法
• 新しい「C-FOG質問票」で、どのような場面ですくみ足が出やすいかを詳細に評価
• 8種類の歩行課題をON/OFFドーパミン状態で実施
• ビデオ評価ですくみ足の割合を算出
• 結果をクラスタリングし、3つのサブタイプに分類
この質問票は、従来の評価法よりも構成妥当性と一貫性が高く、すくみ足を引き起こす状況を明確にできる点が特徴です
(C-FOGQ)characterizing Freezing of Gait questionnaireとは
⇒すくみ足の出現状況をより詳細に把握し,患者に適したすくみ足の軽減方法を見出しやすい質問紙
C-FOGQは,パーキンソン病患者,介護者,研究者との協議を通じて作成された35 項目の自記式による質問紙 C‐FOGQは以下の4つのセクション
SectionⅠ(出現状況):すくみ足の存在,頻度,および治療に対する反応性を評価
SectionⅡ(出現頻度):すくみ足が誘発される状況と頻度を評価
SectionⅢ(戦略):すくみ足を軽減するために一般的に用いられている対応方法の有効性を示す評価
SectionⅣ(すくみ足以外のすくみ):上肢のすくみなど,すくみ足とは異なるすくみの存在と重症度を評価
見つかった3つのタイプ
- 非対称性型
- 不安型
- 感覚・注意型
暗闇、散らかった環境、二重課題など、注意の切り替えが必要な状況ですくみ足が出現しやすいタイプ
認知機能(セットシフト能力)との関連が示唆
この論文が特別な理由
この研究は、「すくみ足は一枚岩ではない」という事実を裏付けました。
• 従来:すくみ足=単一の現象として扱われてきた
• 今後:背景にある「運動・不安・注意」の違いを踏まえてアプローチ
つまり、同じ“足が止まる”症状でも、原因や対策が人によって異なる可能性が高いのです。
これは、すくみ足に対するリハビリを個別化するための重要な知見です 。
リハビリへのヒント
ご自宅で簡単にできる練習を紹介
それぞれのサブタイプに応じたアプローチ例を考えてみましょう。
- 非対称運動型
• 左右差を補う荷重練習や体幹回旋の誘導
⇒片脚立ち、スクワット、ステップ練習など
• 方向転換の練習
⇒大きな円から小さな円へ、速度や環境を変えて練習
- 不安型
•止まってから進むを練習
⇒焦らず一呼吸をおいて一歩目を出す
• 呼吸法とリズム ⇒吸って、吐いて、一歩という合図を活用
•セルフトークの導入
⇒「落ち着いて、一歩ずつ」など自分に声を掛けながら歩行
- 感覚・注意型
• デュアルタスク練習を段階的に導入
例)足踏み+数唱→足踏み+引き算→歩行+会話など
•環境調整 ⇒明るい環境や整理された環境から練習を始める
• 外的キュー(床のラインやメトロノーム)で安心感をプラス
このように、タイプ別の視点を持つことで、より実践的なリハビリ戦略が立てやすくなります。
おわりに
パーキンソン病の方やご家族にとって、「足が急に止まるすくみ足」は日常生活の安全や自由を大きく制限する症状です。
これまで、すくみ足は一括りに語られがちでしたが、本研究はその常識に一石を投じました。
すくみ足には、運動の左右差が強い人、緊張や不安で凍結する人、注意力や環境への反応で凍結する人など、タイプの違いが存在することが明らかになったのです。
つまり、同じ“足が止まる”症状でも、その原因や出方は人によって異なります。
例えば、方向転換で止まってしまう人には歩行環境を工夫した練習を、緊張で足が出ない人にはリラックス法を、注意が必要な人には段階的なデュアルタスク訓練を組み合わせる。
これまで一律だった対応が、「その人に合った」リハビリ戦略に変わる可能性を示しています。
すくみ足は決して「乗り越えられない壁」ではありません。
タイプに応じた工夫を積み重ねることで、歩きやすさや安心感は必ず変わっていきます。
あなたの一歩には、必ず方法があります。
そして、その一歩を支える工夫を一緒に探していくことが、リハビリの大切な役割です。
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡によるセミナーのご案内
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡では、施設での対面式とオンラインを併用して定期的にセミナーを開催しております。
主に、臨床思考力に焦点を置いた「クリニカルリーズニング」、痛みのリハビリに特化した「ペインリハビリテーション」、脳卒中リハビリに特化した「脳卒中リハビリ関連戦略」の3本を定期開催しております。
詳しい内容や日時については、こちらのページをご覧ください。
開催テーマ・日程一覧ペインリハビリテーション-基礎メカニズム編-肩の痛みや膝の痛み、腰痛含め全てのリハビリテーションにつながる”痛み”のメカニズム全ての内容が世界中で行われている研究結果に基づいた講義になっており[…]
皆様の明日の臨床を確実に変えられるような、そんなセミナーとなっております。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡の店舗案内
- 博多店
住所:福岡県福岡市博多区諸岡3丁目10-20
駐車場:3台
アクセス:西鉄井尻駅から徒歩10分/JR笹原駅から徒歩10分
- 小郡店
住所:福岡県小郡市小郡2200-1
駐車場:5台
アクセス:鳥栖JCTから車で5分/JR久留米駅から車で24分
備考:久留米市・筑紫野市/佐賀県鳥栖市・基山町から車で約30分圏内