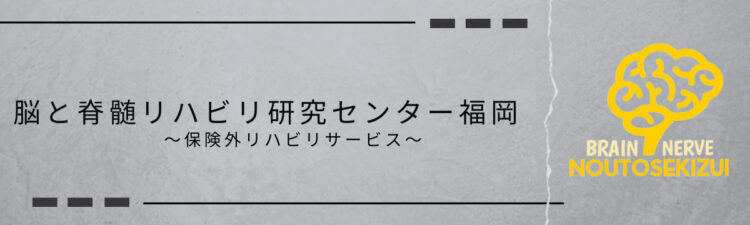この投稿は、『〜脳卒中・脊髄損傷特化型自費リハビリ施設〜脳と脊髄リハビリ研究センター福岡』が日々脳卒中(脳梗塞・脳出血)や脊髄損傷、脳性麻痺といった神経疾患後遺症のリハビリテーションに従事する医療従事者の方や、当事者の皆様に向けて発信するエビデンス情報です。 今回のテーマは「歩きにくさの正体は?」です。


脳卒中を経験された方の中には このような「歩きにくさ」 に悩まれている方も多くいらっしゃいます。 これまで、筋肉の硬さ(痙縮)や筋力低下が主な原因と考えられてきましたが、最新の研究では、歩きにくさには特徴的なパターンがあり、それが歩行の困難さ(重症度)の違いに関係している可能性があることが分かってきました。
今回は2025年に発表された研究をもとに、歩きにくさの正体に迫りながら、パターンごとの改善方法について紹介します。
【脳卒中リハビリ】膝が曲がらない歩き方にはパターンがある?
参考文献
今回の論文は2025年に発表された論文です。
はじめに
脳卒中後の歩行の中でも、Swing期(足を後ろから前に振り出す時)の膝の曲がりが乏しい「スティッフニー歩行(SKG)」は、つま先の引っかかりや代償動作を引き起こし、転倒や歩行効率の低下につながります。これまで痙縮や筋力低下など、さまざまな原因が指摘されてきましたが、リハビリ介入の効果には個人差が大きく、「なぜ同じような歩き方なのに治り方が違うのか」についてははっきりとした答えがありませんでした。そのような中で、今回紹介する研究は、「スティッフニー歩行(SKG)には歩き方に特徴的なパターンがあるのでは?」という新しい視点から分析を行いました。
研究の概要
対象者
- 脳卒中後にスティッフニー歩行(SKG)が見られる患者50名
- 年齢と性別を揃えた健常者15名
方法
歩行中の体の動きを、次の3つの視点から記録・分析しました。
- 運動学(Kinematics)
体の関節がどのように動いているかを測定。
65個のマーカーを体に貼り付け、12台のカメラで動きを記録。 - 運動力学(Kinetics)
地面を押す力や関節にかかる力(トルク)を測定。
トレッドミルの床に埋め込まれた力センサーを使用。 - 筋活動(EMG)
主要な下肢筋8カ所の筋肉(内側腓腹筋、ヒラメ筋、前脛骨筋、内側広筋、外側ハムストリングス、内側ハムストリングス、大腿直筋、中殿筋)の活動量を記録。
これらのデータは、歩行サイクル(片足が地面に着いてから再び同じ足が着くまで)に合わせて細かく分析されました。
スティッフニー歩行(SKG)のパターン分類方法
一般的にスティッフニー歩行(SKG)は「膝が曲がらないこと」で分類されることが多いですが、今回の研究では膝の曲がり具合ではなく、特に次の2つの代償動作に注目しました。
- 骨盤を持ち上げる動き
- 足を外側に振る動き(股関節外転)
これらの「横方向の動き(前額面動作)」が、歩行中にどのように現れるかを分析し、時系列カーネルk-meansクラスタリングという手法で、特徴的なパターンごとに分類しました。
評価項目
各グループについて、次の指標を比較しました。
- 歩行速度
- Swing期の膝の曲がり角度(ピーク屈曲角度)
- 地面を蹴り出す推進力の左右差(propulsion asymmetry)
- 関節の動きや力(運動学・運動力学)
- 筋肉の活動パターン(EMG)
- 筋モジュール(筋シナジー)の数と構成
- 運動制御の複雑さ(Dynamic Motor Control Index:DMCI)
研究の結果
この研究では、歩きにくさのパターンは以下の3つに分類されました。
パターンA(骨盤を大きく持ち上げる)
最も歩きにくさが強い
- 膝がほとんど曲がらない
- 骨盤を大きく引き上げる
- 歩行速度が最も遅い
- 左右の足の推進力に大きな差がある
パターンB(骨盤挙上+足を外に振る)
中等度の歩きにくさ
- 骨盤を持ち上げながら、足を外に振る(股関節外転)
- 膝は多少曲がる
- 歩行速度は中間
- 外見上、歩き方が大きく乱れる
パターンC(代償動作が少ない)
比較的歩きやすい
- 膝が比較的しっかり曲がる
- 骨盤や足の代償動作がほとんどない
- 歩行速度も速く、左右差も少ない
リハビリへの応用
この研究では、筋肉の使い方(EMG)や神経の制御(DMCI)について、高次の協調パターンには明確な違いは見られませんでした。(※なお、個別の筋肉活動(特に内側広筋や外側ハムストリングス)には差が観察されています。)
つまり、歩き方の違いは筋肉の使い方が悪いからではなく、歩行の困難さの段階によって生じている可能性が高いと示されました。そこでリハビリではパターンA → パターンB → パターンCへと、歩行の困難さを軽減していくことが目標となります。
パターン別リハビリのポイント
パターンA(骨盤挙上:膝がほぼ曲がらず、足を出すために骨盤を引き上げて代償している)
目標:Swing期(足を後ろから前に振り出す時)の膝の屈曲を引き出す
- 立脚終期(後ろ脚の蹴り出し)の強化
- 膝を自然に曲げる練習
パターンB(骨盤挙上+外転:膝は多少曲がるが、足の振り出しに外転を伴う)
目標:まっすぐ前に足を出せるように動作を修正する
- 足を外に振らずに真っ直ぐ出す練習(鏡等で確認するとより良い)
- 段差昇降など股関節屈曲と膝屈曲を同時に使う練習
パターンC(代償動作ほぼなし)
目標:より実践的な歩行課題に対応できるようにする
- 歩行スピードを上げるチャレンジ
- 不整地歩行や方向転換(ターンやジグザグ歩行など)練習
- 障害物回避など実生活に近い課題練習
おわりに
この研究は、膝が曲がらない歩き方の違いが、筋肉の使い方ではなく「歩行の困難さ=代償しないと歩けない状態」の違いから生まれていることを示しました。
当事者の皆様には「この歩き方は、今できる最善の方法だったんだ」と前向きに受け止めていただけたらと思います。
そして、セラピストの皆様には、見た目の代償動作だけに惑わされず、「なぜその動きが必要なのか?」を見抜き、パターンA→B→Cへと困難さを減らしていく支援を実施していいただけたらと思います。
このコラムが皆様の歩くにくさの改善に繋がれば幸いです。
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡によるセミナーのご案内
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡では、当施設を利用して定期的にセミナーを開催しております。
一回のセミナーの参加人数が24名で開催しているため質疑応答等も行いやすく、終了後モヤモヤが残ったままにならないように徹底したディスカッションを中心に行っております。
セミナーのテーマは2つに絞っております。
- 『ペインリハビリテーション』
- 『クリニカルリーズニング』
この2本を月毎に開催しております。
詳しい内容や日時については、こちらのページをご覧ください。
開催テーマ・日程一覧ペインリハビリテーション-基礎メカニズム編-肩の痛みや膝の痛み、腰痛含め全てのリハビリテーションにつながる”痛み”のメカニズム全ての内容が世界中で行われている研究結果に基づいた講義になっており[…]
皆様の明日の臨床を確実に変えられるような、そんなセミナーとなっております。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡の店舗案
- 博多店
住所:福岡県福岡市博多区諸岡3丁目10-20
駐車場:2台
アクセス:西鉄井尻駅から徒歩10分/JR笹原駅から徒歩10分 - 小郡店
住所:福岡県小郡市小郡2200-1
駐車場:5台
アクセス:鳥栖JCTから車で5分/JR久留米駅から車で24分
備考:久留米市・筑紫野市/佐賀県鳥栖市・基山町から車で約30分圏内