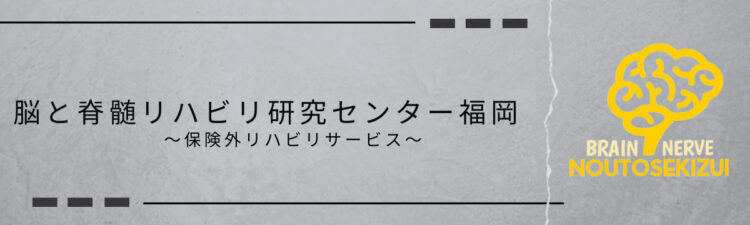この投稿は、『〜脳卒中・脊髄損傷特化型自費リハビリ施設〜脳と脊髄リハビリ研究センター福岡』が日々脳卒中(脳梗塞・脳出血)や脊髄損傷、脳性麻痺といった神経疾患後遺症のリハビリテーションに従事する医療従事者の方や、当事者の皆様に向けて発信するエビデンス情報です。
今回のテーマは「歩行時の膝の過伸展に対するリハビリ方法を比較してみよう!」です。
脳卒中を経験された方で、歩く時に「足が棒のようになってしまう」、「膝がピンと伸びてしまって歩きづらい」といった膝の過伸展(反張膝)と呼ばれる症状に、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
私の担当する患者様の中にも歩行時の膝の過伸展に悩まれている方がいらっしゃいます。
その方々から先日、このような質問を受けました!


そこで今回は膝の過伸展に対するリハビリ方法を最新の研究に基づいて比較し、特に日常生活で皆様が取り入れやすいアプローチに焦点を当てて解説していきたいと思います。
このコラムを通して、日々膝の過伸展に悩まれている当事者の皆様や医療従事者の方のリハビリに役立てていただけたら幸いです。
【脳卒中リハビリ】膝の過伸展に対するリハビリ方法を比較してみよう!
研究の概要に入る前に
膝の過伸展に対するリハビリ方法には、以下の3つのアプローチがよく使用されています。
研究の概要に入る前に、それぞれの方法の効果と限界を整理しどの方法が最も適しているかをみていきたいと思います。
装具療法
これは装具を使用して膝の過伸展を抑える方法です。
Portnoy et al.(2015)の研究ではヒンジ付きソフト膝装具を装着することで、装着中は膝の過伸展が完全に抑制され歩行速度も改善されたとあります。
しかし、装具を外すと再び過伸展が発生することが多く、装具に依存したたけでは長期的な改善には至らないことが指摘されています。
バイオフィードバック
バイオフィードバックはリアルタイムで膝の角度や動作をフィードバックする方法です。
Morris et al.(1992)の研究ではバイオフィードバックを使用することで膝の過伸展が有意に減少したとあります。
しかし、バイオフィードバックにはセンサーや専用機器が必要で、日常生活に継続的に取り入れるには設備面での制約があることが課題となります。
固有感覚トレーニングとプロウリング
固有感覚トレーニングとプロウリングは膝など下肢の筋肉や関節の位置感覚を改善する方法です。
Dalal et al(2018)の研究では、片足立ちやスクワットを通じて膝の過伸展が減少し、歩行速度が改善したとあります。
プロウリングは膝を軽く曲げた状態で前傾姿勢を保ちながら歩行することで、膝の過伸展を効果的に抑制します。
この方法は特別な機器が不要であり、日常生活に取り入れやすいことが大きな利点です。
では、研究の内容に入っていきましょう!
参考文献
今回の論文は2021年に「Gait&Posture」誌に発表された論文です。
Treatment of knee hyperextention in post-stroke gait A systematic review,Marieke-Geerars他,2021
研究の目的
このシステマテックレビューでは上記の3つのリハビリ方法に加えて、運動再学習プログラム(MRP)、装具療法、全身振動トレーニング、機能的電気刺激(FES)といったリハビリ方法も含めて、それぞれの膝の過伸展に対する効果を比較し、最も有効なアプローチを検討しています。
対象者
このシステマティックレビューに含まれる8つの研究では以下の方が対象となりました。
- 脳卒中発症後0ヶ月~56年の急性期および慢性期の方
- 歩行時に膝の過伸展がみられる方
研究方法
このシステマティックレビューでは以下の8つの研究が分析されました。
【Guo et al.(2015)】
対象者:脳卒中発症後0~3ヶ月の30名
介入内容:実験群には8週間の全身振動トレーニング、コントロール群は振動なしで同様のトレーニングを実施
結果:実験群では膝の過伸展が減少し、歩行速度が向上した。
【Dalal et al.(2018)】
対象者:脳卒中発症後急性期および亜急性期の32名
介入内容:実験群にはプロウリング(膝を軽く曲げて前傾姿勢で歩行する練習)と固有感覚トレーニング(片足立ちやスクワットなど)を6~10日間実施、コントロール群は通常の理学療法を実施
結果:実験群では膝の過伸展の角度が有意に減少し、歩行速度も改善した。
【Morris et al.(1992)】
対象者:脳卒中発症後1~3カ月の26名
介入内容:実験群には8週間の運動再学習プログラム(MRP:歩行練習などを反復して行う)にバイオフィードバック(センサーを使用し膝の角度をリアルタイムでフィードバック)も追加で実施
結果:実験群では膝の最大伸展角度が有意に減少し、過伸展の頻度も減少した。
【Lee et al.(2017)】
対象者:脳卒中発症後4~10カ月の18名
介入内容:誘導チューブを使用したトレッドミル歩行(GTG)と従来のトレッドミル歩行(CTG)の比較
結果:誘導チューブを使用した群では、膝の過伸展角度が有意に減少し、筋電図における筋活動のバランスも改善された。
【Ceceli et al.(1996)】
対象者:脳卒中発症後0~1年以上の41名
介入内容:実験群には膝の過伸展を抑制するためのバイオフィードバックトレーニングを実施、コントロール群は理学療法のみを実施
結果:実験群では膝の過伸展の頻度が減少したが、歩行速度には有意な変化はなかった。
【Portnoy et al.(2015)】
対象者:脳卒中発症後3カ月~25年の31名
介入内容:ヒンジ付きソフト膝装具を4週間装着、その後4週間は装具を外して観察
結果:装具使用中は膝の過伸展が完全に抑制され、歩行速度が改善した。しかし装具を外すと再び過伸展は発生した。
【Boudarham et al.(2013)】
対象者:脳卒中発症後6~56年の11名
介入内容:KAFO装具装着時と非装着時の歩行を比較
結果:KAFO装具装着時に膝の過伸展が減少し、歩行速度も向上した。
【Bae et al.(2019)】
対象者:脳卒中発症後6ヶ月以上の12名
介入内容:裸足歩行、足関節装具(AFO)装着、足関節背屈筋に対する機能的電気刺激(FES)の各リハビリを比較
結果:いずれの方法も膝の過伸展や歩行速度に関しての有意な変化はなかった。
リハビリへの応用
これらの研究の中で取り上げられたリハビリ方法にはそれぞれ効果が確認されていますが、いくつかの限界もあります。
装具療法は装具に依存する点で長期的改善が難しく、バイオフィードバックや電気刺激(FES)は専用の機器が必要なため、日常的に実施するには難しいことが課題です。
また振動トレーニングやチューブを使った歩行、運動再学習プログラムなどは特別な設備やサポートが必要となります。
その中で固有感覚トレーニングとプロウリングは、日常生活に取り入れやすく、膝の過伸展を改善するために有効な方法です。
以下にこれらのリハビリへの応用ポイントをまとめます。
固有感覚トレーニング
片足立ちやスクワットのような基本的な運動を通じて、膝の位置感覚や筋力を向上させることができます。
軽く膝を曲げた状態を保ちつつ、筋肉のバランスを整えることで過伸展の軽減に繋がります。
プロウリング
膝を軽く曲げた状態で前傾姿勢を保ちながら歩行する練習です。
日常生活でも簡単に取り入れられるため、固有感覚トレーニングと組み合わせて行うことで効果的なリハビリとなります。
これらのトレーニングを行うことで、膝の安定性が向上し、歩行中の過伸展を抑える効果が期待されます!
結論
膝の過伸展に対するリハビリ方法として、装具療法やバイオフィードバックは短期的に効果を発揮しますが装具に依存せず長期的な改善を目指すためには固有感覚トレーニングやプロウリングが特に有効と考えられます。
これらのアプローチを継続して行うことで、長期的に安定した歩行パターンを獲得し日常生活の動作がよりスムーズになることが期待されます。
おわりに
今回のコラムでは膝の過伸展に対するリハビリ方法を比較し、その有効性について解説しました。
装具療法やバイオフィードバックはもちろん効果的な方法ですが、皆様が日常生活で取り入れやすいのは固有感覚トレーニングやプロウリングだと思います。
これらは特別な機器も必要なく、今からでも簡単に始められるので是非試してみてくださいね。
毎日コツコツと継続することで、着実に改善に繋がっていきます!
膝の過伸展が改善し、歩行の質が上がることでより快適な生活を取り戻すための一歩になれば幸いです。
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡によるセミナーのご案内
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡では、当施設を利用して定期的にセミナーを開催しております。
一回のセミナーの参加人数が24名で開催しているため質疑応答等も行いやすく、終了後モヤモヤが残ったままにならないように徹底したディスカッションを中心に行っております。
セミナーのテーマは2つに絞っております。
- 『ペインリハビリテーション』
- 『クリニカルリーズニング』
この2本を月毎に開催しております。
詳しい内容や日時については、こちらのページをご覧ください。
開催テーマ・日程一覧ペインリハビリテーション-基礎メカニズム編-肩の痛みや膝の痛み、腰痛含め全てのリハビリテーションにつながる”痛み”のメカニズム全ての内容が世界中で行われている研究結果に基づいた講義になっており[…]
皆様の明日の臨床を確実に変えられるような、そんなセミナーとなっております。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡の店舗案内
- 博多店
住所:福岡県福岡市博多区諸岡3丁目10-20
駐車場:2台
アクセス:西鉄井尻駅から徒歩10分/JR笹原駅から徒歩10分
- 小郡店
住所:福岡県小郡市小郡2200-1
駐車場:5台
アクセス:鳥栖JCTから車で5分/JR久留米駅から車で24分
備考:久留米市・筑紫野市/佐賀県鳥栖市・基山町から車で約30分圏内