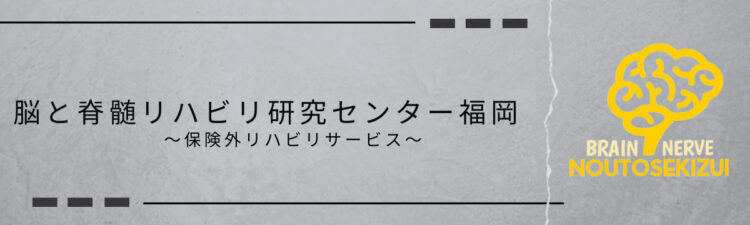この投稿は、『〜脳卒中・脊髄損傷特化型自費リハビリ施設〜脳と脊髄リハビリ研究センター福岡』が日々脳卒中(脳梗塞・脳出血)や脊髄損傷、脳性麻痺といった神経疾患後遺症のリハビリテーションに従事する医療従事者の方や、当事者の皆様に向けて発信するエビデンス情報です。
マッサージ機のようなもので特定の筋肉に振動刺激を与えるものを「局所振動刺激」
プレートのようなものを用いて全身に振動刺激を与えるものを「全身振動刺激」
と言います。
今回は、脳卒中後振動刺激機器を用いる際の効果的なやり方について、科学的根拠に基づいて解説します。
痙縮に対する振動刺激療法の効果と実践方法
研究の概要
脳卒中後の痙縮(筋肉の強張り)がある患者に対する振動刺激療法の有効性を検証するための無作為化比較試験(RCT)を対象としたシステマティックレビューおよびメタアナリシス。
研究の結論
振動刺激療法は上肢の痙縮を有意に減少させるが、下肢への効果については不明確
疼痛を軽減させる効果がある
運動機能を向上させる効果がある
歩行機能への効果は不明確
研究の背景
脳卒中後に生じる痙縮の問題点には関節の拘縮、痛み、筋力の低下、異常姿勢や歩行、活動や社会参加の制限を引き起こします。
痙縮に対する非薬物療法の1つである振動刺激療法は、機械的な振動により神経や筋肉を刺激して治療効果を発揮する物理療法のひとつです。
脳卒中後の痙縮に対する効果が報告されていますが、最適な条件については一貫した見解がないのが実情です。
研究の目的と対象となった研究
【研究の目的】
脳卒中後の痙縮に対する振動刺激療法の効果を分析し、実施時間や振動をあてる部位などで痙縮にどのような効果をもたらすか詳細に検討することを目的としています。
【対象となった研究】
対象となった研究:12研究、13試験(1つの研究は試験を2つ実施)
研究の種類:すべて無作為化比較試験(RCT)
対象患者の特徴
研究に参加した患者の総数: 442名
年齢:平均約40〜77歳(例:66±13歳、63±8.5歳など)
性別:各研究で男女の比率が異なる
発症からの期間:発症から6ヵ月以上(慢性期を対象)
痙縮の部位:上肢(肩・肘・手首)および下肢(膝・足首)
介入の方法
- 振動刺激の方法について
全身振動刺激(WBV): 6研究 – 振動プラットフォームを用いて下肢などから全身に振動を伝達
局所筋振動刺激(LMV): 7研究 – 振動デバイス(マッサージ機等)を痙縮が起きている筋または拮抗筋(痙縮が起きている筋肉の反対側の筋肉)に直接当てる - 振動刺激の種類や頻度・時間など:
・振動の周波数: 4試験は20Hz以下、9試験は20Hz以上
※周波数=1秒間に振動する”回数”のこと
・1回の治療時間: 5分、5~30分、または30分
・治療回数: 1試験のみ1回のみ、12試験は複数回実施
・治療頻度: 2回/週(2研究)、3回/週(8研究)、5回/週(2研究)
・治療期間: 主に2〜6週間
アウトカム(効果判定)に用いられた検査項目
主要評価項目
Modified Ashworth Scale (MAS: 修正Ashworth スケール)
=6段階で数字が大きくなるほど痙縮が強いと判断する検査
その他の検査項目
歩行能力:TUG、10MWT、6MD等
疼痛:VAS等
研究から導き出された最適な振動刺激の方法
研究結果を臨床に落とし込む考え方
今回の研究結果から、特に上肢(肩や肘)の痙縮には有効であり、
- 周波数は20Hz以上
- 1回あたり30分
- 週に5回
この3つが推奨される振動刺激のパラメーターです。
研究内容を確認する限りでは、肩や肘に対しては100Hz近い高周波数が用いられています。
尚、振動刺激療法の下肢・歩行機能に関する有効性については、2023年時点では明確なエビデンスが不足しています。
安全性については概ね安全で、有害事象は軽微かつ一過性です。(筋肉痛等があったのみ)
短期効果は確認されましたが、長期的な効果については不明なため更なる研究が必要です。
今回のメタアナリシス手法では、統計的に有意な効果があったと示されたのは「肩、肘」に対する振動刺激療法です。
上肢(肩や肘)の痙縮があり、リハビリの内容に制約が生じてしまうような場合、
運動前に局所振動刺激を痙縮が生じている筋肉に対して、30分程実施して痙縮が緩和させ、運動が行いやすい状態になってからリハビリを進める
というのが、有効な使い方となると思われます。
当事者の方が自ら行えるのであれば、
リハビリの直前30分間実施してもらい、その後にセラピストがリハビリを行う方法であればリハビリの効果を最大限引き出せる可能性があります。
さらに、1回だけ行うのではなく、週5回などなるべく頻度を多くすることも重要です。
振動刺激の効果的な方法まとめ
研究手法の前提として、メタアナリシスという研究デザインにおいて効果にばらつきが大きかったり、いくつかの研究で効果がない結果が出たりすると、仮に効果のあった研究が含まれていても有意な効果はなかったという結果になります。
例えば、今回の研究では有効とは言えないとした「足首」に対する振動刺激療法ですが、
全身振動刺激療法(12Hz、5~30分)を実施することで痙縮を軽減させたという報告も含まれています。
まだまだ振動刺激療法の実際のパラメーターについては不明な点も多いですが、有害事象の報告も少なく、コストもあまりかけずに当事者の方がご自身でも行えるリハビリの方法です。
麻痺している手足の強張りがあり中々上手く動かせないという方は、振動刺激療法を試してみる価値は十分にあると思われます。
また、振動刺激療法単独では歩行機能の向上にはつながりにくいため、リハビリ前に身体のコンディションを整えるような役割であると考えていただくのが良いです。
~今回の結論となった統計的なデータは以下の通り~
※あくまで”統計的に”有意な効果や差があったかなかったかを示しています
標準化平均差(SMD)=異なる検査の結果であっても差を比較することのできる指標(1に近いほど効果が大きい)
95%信頼区間(95%CI)=知りたい値がほぼ確実にあるだろうといえる区間(0をまたぐ(例0.3~-0.3)と有意でないと判断される)
H²=研究間での結果のバラつきの指標(大きいほどバラつきが大きい ※3以上の場合は解析そのものを見直す必要がある位のバラつき)
P値=効果がないと仮定した時、観察や研究で示された結果(かそれ以上の結果)が偶然でる確率(が0.01や0.05以上だと偶然起きるだろうから有意な差でないと判断される)
痙縮:有意な改善を示した
(SMD=-0.77 95%CI=-1.17〜-0.36)
疼痛:有意な改善を示した
(SMD=-1.09 95%CI=-1.74〜-0.45)
運動機能:有意に向上した
(SMD=0.42 95%CI=0.21〜0.64)
歩行機能:有意な差はなく、効果は不明確
(SMD=-0.23 95%CI=-0.56〜0.10)
振動刺激の種類(局所振動刺激全身振動刺激)による違い
・局所振動刺激:SMD=−0.99、95%CI=−1.57~−0.40
・全身振動刺激:SMD=−0.59、95%CI=−1.13~−0.05)
振動の時間による効果の違い
・30分:有意な効果あり
(SMD=−0.91、95%CI=−1.40~−0.43、H²=2.85、P=<0.01)
・5分~30分:有意な差はなし
(SMD=−0.68、95%CI=−1.49~0.13、H²=6.40、P=0.10)
・5分:有意な差はなし
(SMD=−0.37、95%CI=−1.04~0.31、H²=なし(1研究のみのため)、P=0.29)
部位による効果の違い
・足首:有意な効果なし
(SMD=-0.86、95%CI=-2.19~0.47、H²=12.57、P=0.00)
・膝:有意な効果なし
(SMD=0.00、95%CI=-0.37~0.37、H²=1.00、P=1.00)
・手首:有意な効果なし
(SMD=-0.49、95%CI=-1.26~0.28、H²=4.44、P=0.00)
・肘:有意な効果あり
(SMD=-0.87、95%CI=-1.40~-0.34、H²3.09、P=0.00)
・肩:有意な効果あり
(SMD=-0.47、95%CI=-0.93~-0.01、H²=1.29、P=0.28)
周波数による効果の違い
・20Hz以下:有意な効果なし
(SMD=-0.85、95%CI=-1.77~0.07、H²=7.88、P=0.00)
・20Hz以上:有意な効果あり
(SMD=-0.75、95%CI=-1.20~-0.29、H²=3.08、P=0.00)
実施の頻度による効果の違い
・2回/週:有意な効果なし
(SMD=-0.59、95%CI=-1.21~0.02、H²=1.00、P=0.98)
・3回/週:有意な効果あり
(SMD=-0.60、95%CI=-1.10~-0.09、H²=4.09、P=0.00)
・5回/週:有意な効果あり
(SMD=-0.74、95%CI=-1.16~0.31、H²=1.00、P=0.68)
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡によるセミナーのご案内
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡では、対面(福岡)やオンラインにて定期的に理学療法士・作業療法士向けのセミナーを開催しています。
詳細やセミナー一覧については、以下の特設サイトよりご覧ください。
脳と脊髄リハビリ研究センター福岡の店舗案内
- 博多店
住所:福岡県福岡市博多区諸岡3丁目10-20
駐車場:3台
アクセス:西鉄井尻駅から徒歩10分/JR笹原駅から徒歩10分 - 小郡店
住所:福岡県小郡市小郡2200-1
駐車場:5台
アクセス:鳥栖JCTから車で5分/JR久留米駅から車で24分
備考:久留米市・筑紫野市/佐賀県鳥栖市・基山町から車で約30分圏内